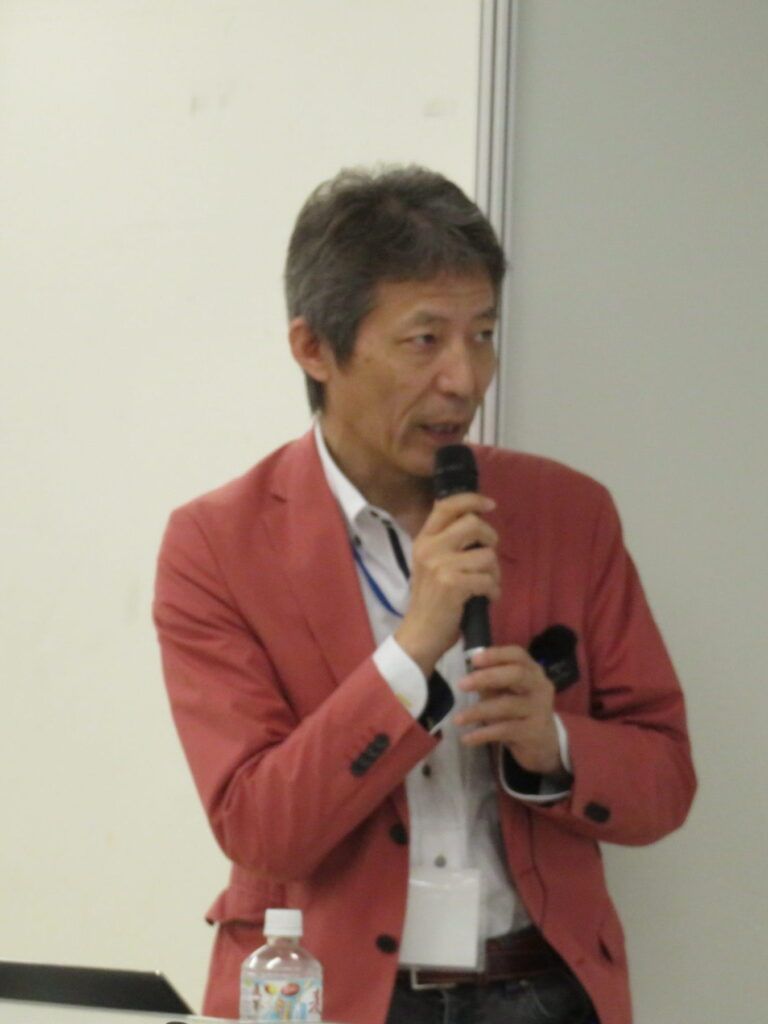イメージ・マジック AIと自動化技術の融合 山川社長が語るオーダーグッズビジネスの変革期
オーダーグッズ業界最大級の展示会「オーダーグッズビジネスショー2025」が9月30日と10月1日の2日間、東京・池袋のサンシャインシティ展示ホールDで開催された。会場には一般企業やクリエイターを含む79社が出展し、オリジナルグッズ製作の最新技術や製法を披露。UV転写用プリンターやDTFプリンター、小型レーザー機など、多彩な製造機器が集結し、オーダーグッズ業界の今と未来を示した。
会期中には、株式会社イメージ・マジックの代表取締役社長(CEO)・山川誠氏によるセミナー「AIと自動化を活用したオーダーグッズビジネスの未来像」が行われた。その講演内容を紹介する。
「省人化と自動化」への潮流
山川氏は、アメリカのDTFプリント工場や中国の工場などを訪れる中で、著しく成長している企業には共通する戦略があると語る。それは、省人化を徹底的に推進し、人的コストを削減して効率性を最大化する取り組みである。
実際に山川氏が訪れたアメリカのDTF専門工場では、今年1月の時点で1日1万枚の生産だったものが、直近では1日6万枚にまで拡大していたという。
この背景には、徹底した自動化と省人化の推進がある。同氏は「私たちが学ぶべき点はそこにある」と指摘する。さらに、自動化を進めるにあたっては、単に工程を追加するのではなく、「そもそもその工程が本当に必要なのか」を常に全員で議論し、見直しを行っている点が印象的だったと述べた。急成長する企業の共通項として「徹底した自動化」を挙げ、人手を増やすのではなく、省人化と効率化に徹底的に振り切る発想こそが、競争優位を生み出すと語った。
イメージ・マジックが実践する「5つの自動化アプローチ」
同社は自社工場を実験の場とし、以下の5領域で自動化を強化している。
一つ目はソフトウェアによるアプローチ、二つ目はハードウェア、三つ目は見える化、四つ目は仕組みや運用の変更、そして五つ目がAIの活用である。山川氏は、こうした多角的なアプローチが省人化において必要だと指摘する。
まずソフトウェアについてである。これは受注データ処理の仕様に関わる部分で、同氏によれば、同社では2009年に受注の自動化を開始した。Web上で誰でも簡単に注文できる仕組みを作り、デザイン部門と工場との連携を重視したという。単にデザインするだけでは他社と同様の普通のデザイン部門にとどまるが、そこから生産管理システムを通して工場にデータ連携することにより、全体最適化を実現することを重視したと述べた。
印刷工程の自動化・省人化についても説明した。2011年頃からDTGを中心に取り組み、二次元コードを読み取るだけでデータを取り込める仕組みを整えた。デザインツールで入稿されたデザインは自動的にサーバーにアップロードされ、バッチ処理によって印刷データが生成される。その後、二次元コードを読み取ることで印刷サイズに自動的に合わせることが可能となった。これにより、生産時間は従来の約5分の1に短縮されたという。
山川氏はさらに、受注データ処理の効率化が収益に直結することを強調する。以前は1枚の注文でも100枚の注文でも処理時間はほとんど変わらず、むしろ少量注文の方が時間がかかる場合もあったという。現在は「1秒1円」で原価計算を行い、受注処理時間の削減が直接的な収益向上につながると説明した。
次にハードウェアの取り組みである。DTGのデジタルラインでは、前処理から乾燥までを自動化する装置を導入して省人化を実現した。またDTFでは、カッターにフィルムの保安センサーを搭載して、作業終了後に自動でカットする装置を開発した。さらに、たたみ袋装置や自動搬送装置など、さまざまなハードウェアの導入によって効率化を進めていると述べた。
カメラ技術とMESシステムで生産現場を「見える化」
現在開発中の装置では、UVプリンターにカメラを搭載し、印刷物をカメラで認識して処理する仕組みを構築している。従来のUVプリンターでは、印刷時にマスキングテープを周囲に貼る必要があったが、この装置ではそれが不要である。山川氏は、これを完全自動化の第一歩と位置付け、作業コストがかからず、誰が操作しても失敗しない仕組みの重要性を強調した。特に、属人的な作業を排除するうえで、異物や汚れを検知する高度なカメラの役割が大きいと語った。
さらに、同氏は「見える化」の重要性を説く。工場には監視カメラを設置しており、異物や汚れの混入などクレーム発生時の確認が可能である。現在、全工場で自動化により監視カメラが稼働し、何時何分にどこを通ったかの記録が残る仕組みとなっている。これにより、従来必要だったクレーム対応のための過剰な対策時間が不要になったという。
山川氏は次にMESシステムについて説明した。MESシステムはプリンターの稼働状況を可視化する仕組みである。現場作業者は、離れざるを得ない場合には機械を停止せざるを得ない。MESシステムは、この停止時間やダウンタイムを分析し、不要な時間を削減することで生産性を向上させる。こうした「見える化」により、継続的に効率改善を行える環境が整ったという。
さらに仕組みや運用の変更についても触れた。同社ではデジタル化を推進し、指示書は以前から廃止している。現場の負担はあるものの、件数の増加を踏まえれば早期に廃止すべきであると考えたという。運用方法の最適化は各社で異なるが、どの工程を削減すべきかを話し合うことで、最適な仕組みが見えてくると指摘した。 山川氏はまた、著作権チェックの自動化についても述べた。Webで入稿されたデザインは自動的に類似画像を確認し、著作権に問題がある場合は印刷を拒否する仕組みである。ただし、断られたデザインが他社で印刷される可能性もあるため、この「見える化」が業界全体に浸透することが、健全な業界の発展につながると強調した。

AIがもたらす入稿・生産・開発の未来像
AIを活用した問い合わせ対応は月間約8,000件を超え、これにより人件費の大幅な削減が可能になっているという。
さらに、社内ナレッジのAI活用についても触れた。新人社員が業務内容を理解する際に発生する「誰かに聞かないとわからない」という課題を解消するため、研修プログラムや社内マニュアルをAIで参照できる仕組みを整備した。これにより、新人教育の効率化が図られているという。
山川氏は、AIによるソフトウェア開発の効率化も紹介した。従来2週間かかっていたソフト開発をAIによって約30分で完了させることが可能となったという。従来の開発費用が約100万円かかっていた場合、この自動化によりコスト削減効果は劇的である。さらに、米国でもエンジニアの採用が減少し、マイクロソフトをはじめとする企業が作業員削減に取り組むなど、AIによる自動化の動きは顕著であると述べた。
次に、入稿デザインにおけるAI活用について説明した。低解像度のデータをAIで高画質化したり、細い線のパウダーが乗らない問題をAIで自動補正したりすることで、印刷時のリスクを低減しているという。さらに、自動塗り足し機能により、入稿データが不足している場合でもAIが補完し、顧客満足度の向上につながると語った。
AIは色数判別にも優れており、目で見た場合3色に見えるデザインでも、実際には26,300色あることを検出可能である。これにより、自動見積もりや印刷方法の提案もAIで実現できると述べた。
山川氏は、AIによってデザインスキルが十分でない人でも、高品質な入稿デザインを作成できる時代が到来すると指摘した。これにより、高齢者や子どもなど、これまでプリントを作ったことのない層でもオーダーグッズを制作できるようになり、市場はさらに拡大すると考えているという。
オーダーグッズビジネスの変革期
AIと自動化の技術がオーダーグッズビジネスを根本から変革する転換期を迎えていると指摘した。省人化・自動化・AI技術の活用により、コスト削減や生産性向上、品質向上を実現し、入稿データと仕上がりの差異を最小化することで顧客満足度の向上につながるという。山川氏は、これらの技術を提供することで、市場拡大に貢献したいと述べた。
さらに、同氏は、自社で培ったノウハウを積極的に提供していく意向を示した。受注システムや生産管理システム、自動化に関わるハード・ソフトの開発など、社内技術はオープンにしているという。自社工場は常に進化を続けており、半年ごとに新たな仕組みに更新されている。今年に入ってすでに三度の刷新を行ったという。工程や仕組みは隠すことなく公開しており、実際に見て確かめてほしいと呼びかけた。
- <出典>
- 講演:「AIと自動化を活用したオーダーグッズビジネスの未来像」
- オーダーグッズビジネスショー2025(2025年9月30日〜10月1日)
- 企業情報
- 株式会社イメージ・マジック
- 〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F
- 企業HP:https://imagemagic.jp/
- 取扱商品:https://store.imagemagic.co.jp/