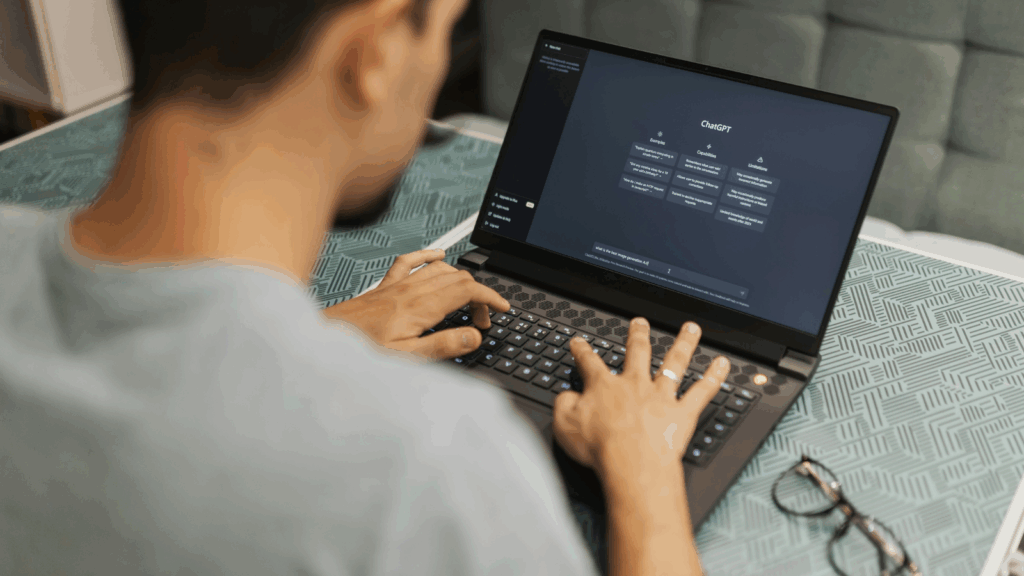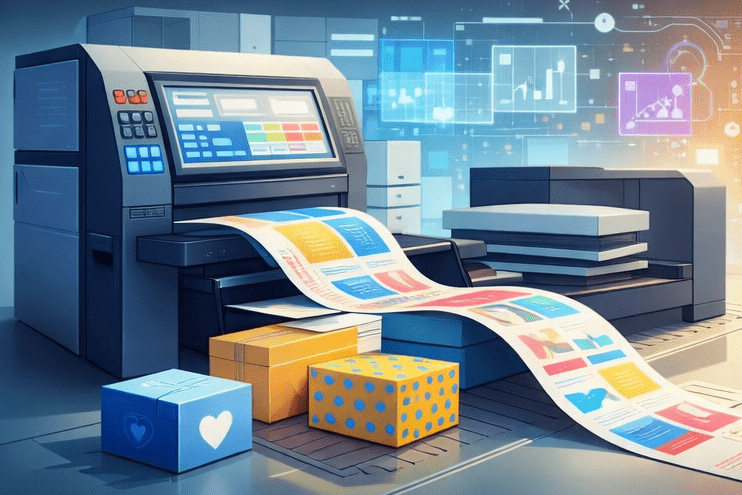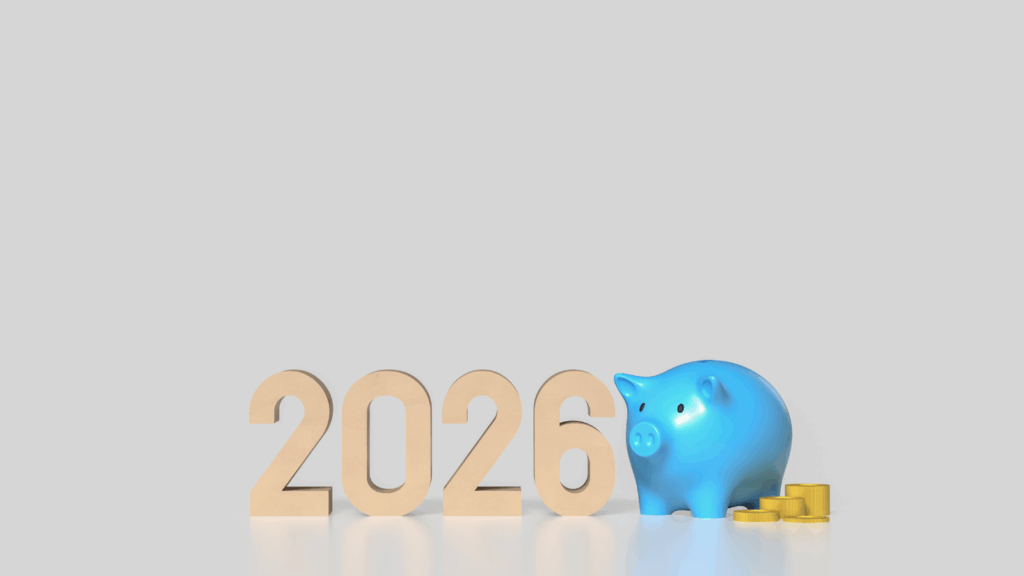【対談・インタビュー】共進ペイパー&パッケージ:鍛治川社長/ソウブン・ドットコム:木村社長 デジタル技術を基軸に業態を変革 印刷×ITで急成長を実現
事業拡大を成し遂げた経営者が対談
ペーパーレス化やAI技術の進展など、印刷業を取り巻く社会は常に変化している。今後は一つの業態に囚われず、需要の変化に合わせて柔軟に戦略を変えるビジネスモデルが求められる。デジタル技術を基軸に業態を変革させ、新たな成長領域を生み出したリーダーたちは、印刷の未来をどう展望しているのか。㈱共進ペイパー&パッケージ代表取締役社長の鍛治川和広氏と㈱ソウブン・ドットコム代表取締役社長の木村崇義氏がそれぞれの意見を交わした。
―まずは両社の事業内容と、新たな成長領域を生み出すまでターニングポイントを伺います。
鍛治川氏
当社は1948年に紙の卸業として創業し、以降、印刷紙器や段ボール事業と様々な事業に進出することで成長を続けてきました。近年のターニングポイントは、2013年にデジタル印刷機を導入し、Webからパッケージを注文できるサービスを立ち上げたことです。私は異業種の企業で経験を積んだのち、2009年に当社に入社しました。当時の私は、「印刷について詳しくないからこそ枠にとらわれないチャレンジをしてみたい」と考え、デジタル印刷を活用した印刷通販サービスに挑戦しました。それが、パッケージ製作サービス「ハコプレ」事業です。
もう一つのターニングポイントでいえば、M&Aですね。ここ4年で3社を取得しました。「ハコプレ」事業の拡大に加え、M&Aにより売上高がグループ合計で107億円まで伸びています。その中でも、前年に「ハコプレ」事業の売上は約20億円に達しました。
木村氏
当社は『創文印刷工業』として1939年に創業し、長年学術誌の印刷を強みとしていました。ターニングポイントとなったのは、デジタルマーケティングを活用した学術団体へのフルサービスを開始したことです。私が2017年に入社した頃、当社の売上構成は印刷物が全体の約99・6%を占めており、ほぼ「学術誌の印刷会社」でした。しかし、印刷だけでは差別化が難しく、競合他社に勝てません。そこで、中小規模の学術団体に対して、イベント運営や事務局機能まで含めた〝フルサービス〟を提供するというビジネスへの転換に動き始めました。ITをマーケティングに活用すれば、この領域に活路を見出せるのではないかと考え、デジタルマーケティングの強化に大きく舵を切りました。
―鍛冶川さんにお聞きします。M&Aでは、どのような会社を取得したのですか?
鍛治川氏
当社のM&A方針は、〝異業種は対象にしない〟ことです。また、一般的には中長期的な〝グランドデザイン〟を描き、それに基づいて対象企業を探していくケースも多いと思います。しかし、当社の場合は少し異なり、サプライチェーン上で関連のある企業の中から、シナジーが見込める相手だけを対象にしています。たとえば〝デザイン領域を強化したいからデザイン会社を探した〟という発想ではなく、〝取引や相談を通じて、組むことで伸びる可能性を感じた相手〟という考え方です。
―木村さんは具体的にはどのようにデジタルマーケティングに取り組みましたか?
木村氏
学術団体の印刷営業の世界には、今もなお古い体質が残っています。営業スタイルは訪問が基本で、団体と企業が何十年も関係を続けてきたケースが多く、極めて密接な関係が形成されています。しかし、多くの印刷会社が人手を減らしたことで、営業担当者が一日中クライアントを訪問して回ることは難しくなっているのが現状です。
大学の教授や事務局担当者は困ったときに助けてくれる印刷会社の営業担当者を頼りにするところがありましたが、それが失われつつあります。そうした状況なので、困った時に調べたいことがあればネットで検索するのでは、と推測したのです。
当社は、学術団体が抱えがちな疑問を徹底的に抽出し、それらを解説するWebページを整備しました。例えばインボイス制度の開始時には、『学会 インボイス』と検索すると当社のWebページが上位表示されるようにしました。制度の概要や手続きをわかりやすく解説しつつ、実務負担が大きい場合は当社の事務代行サービスをご利用下さい、という構成です。同様のページを数百件単位で制作し、問い合わせの獲得につなげていきました。
デジタルマーケティングに取り組み始めたのはコロナ以前でしたが、コロナ禍に入ると予想以上に問合せ件数が急増しました。営業担当者が対面で動けなくなったことにより、学術団体側が情報収集をオンラインに切り替えたのだと考えられます。この期間に当社の企業規模はおおむね3倍に拡大しており、コロナ禍が逆風ではなくチャンスとなりました。
システム構築とデジタルマーケティングが鍵に
―ここまで至るまでに、乗り越えるのが大変だったエピソードはありますか。
木村氏
最も苦労したのは、デジタルマーケティングの効果で事業が急成長した局面でした。私が入社した当初、200団体だった取引先が、現在では約1800団体に増加しています。この成長スピードは経営者としての自身の力量を大きく超えていたと感じます。毎年20人以上を採用する状況となり、コーポレートガバナンスの整備が追いつかず、品質面やコンプライアンス、情報セキュリティといった領域で問題が噴出しました。
急成長がもたらす歪みと正面から向き合わざるを得ず、悩んでいた時に、転機となったのが、鍛冶川さんとの出会いでした。鍛冶川さんにハコプレ事業を通じて急拡大を遂げる過程での苦労をお聞きし、「君が今やっていることを、きちんとやり続ければ大丈夫だ」という一言は、大きな支えとなっています。この言葉を指針として、とにかくやり続けることを決意した結果、現在は企業としての基盤が安定し始めています。
鍛治川氏
私自身も、木村さんとまったく同じような苦労を経験してきました。新規事業によってサービスを拡大し、会社が成長する一方で、組織がそのスピードについていけなくなったのです。経営者として何よりつらかったのは、会社を成長させ、より良い組織にするために立ち上げた新規事業が、結果として社員に大きな負担を強いることになってしまっていたことです。
―お二人はその困難をどう乗り越えましたか?
木村氏
同時多発的に発生した問題の一つひとつに、逃げずに向き合っていくしかなかったですね。人に関する問題で言えば、社員が何に不満を感じているのか、どうすれば少しでも解消できるのかを丁寧に話し合いました。それらの課題は時間をかけて取り組まざるを得ないものばかりでした。
そうした中で、結果的に有効だったと感じているのが、全日本印刷工業組合連合会のCSR認定です。これはガバナンスを構築する上で非常に使いやすい枠組みで、社員に対して「どこを目指すのか」を明確に示すことができます。CSR認定に取り組んだことで社員が同じ方向を向き、一丸となって取り組むための軸に繋がりました。
鍛治川氏
成長に伴う課題を乗り越えるには、やはり成長を遂げて黒字にするしかないですね。成長する過程では必ず投資が必要になりますが、その投資のさじ加減が非常に難しい。成長を見越して生産能力を高めると、どうしてもコストが先行し、赤字になりやすくなります。そのため、成長期であるにもかかわらず赤字が続く、という状況に陥りかねません。
ただ、一定の規模まで事業が成長すると、そうした歪みは調整できるようになります。事業規模が小さいうちは、黒字と赤字の振れ幅が大きく、経営は不安定になりがちです。しかし、一定の規模を超えると、社員の負荷が軽減され、組織全体が楽になってきます。また、黒字が出るようになると、賞与を増額できるようになり、社内の雰囲気が良くなります。「成長して黒字を出す」という状態に到達しなければ、次の段階には進めない。新規事業の目指すべきゴールは、やはりそこにあると考えています。
AIによる効率化と代替不可能な価値を追求
―事業を革新していく中で鍵となったテクノロジーはありますか?
鍛治川氏
デジタル印刷とシステム開発力です。当社の成長の要因は、ハコプレ事業そのものというよりも、企業ごとに個別カスタマイズしたシステムを提供できるようになった点にあります。これが可能になった背景には、Webサービスを立ち上げたことで、社内にIT開発力が蓄積されたことがあります。「こうした仕組みを自分たちでつくれる」という手応えを得られたことが、次の展開につながりました。
さらに重要だったのが、生産管理システムです。各顧客向けのシステムで受注した多様な注文を、共通のデータ形式に変換し、生産工程へ効率的に流す仕組みを構築しました。顧客側のフロントエンドで仕事を集め、その後段でいかに効率化するか、という点がポイントです。
木村氏
当社でも、基幹システムや顧客情報のデータベースが極めて重要な役割を果たしています。約1800の学術団体の情報をデータベース化し、各クライアントが何に関心を持っているのか、現在どのサービスを提供しているのか、次にどのようなクロスセルが可能かといった情報を一元的に管理しています。この情報を元に、メールマガジン配信などを通じて、営業コストを抑えながら必要な情報を適切に届ける仕組みを整えてきました。また、印刷、事務局、イベントという三つの事業を横断的に原価管理する必要があるため、CRM(顧客関係管理システム)の「セールスフォース」をベースに自社で開発し、三つの事業を一元に生産管理できる体制を構築しています。予算規模が限られた学術団体を主な顧客としている以上、収益性を厳密に管理しなければ、そもそも事業として成り立ちません。そうした意味でも、システム基盤の整備は欠かせない要素だったと考えています。
―ITに関わる社内の仕組みは社長ご自身が考案されましたか?
社員と考えを合わせて構築しましたか?
鍛治川氏
当社のITシステムは初めから誰かがグランドデザインを描いて組み立てていったものではありません。7割程度の完成度で形にして、残りの3割は事業に取り組みながら社員たちと共にシステムを改善していきました。そのやり方が、結果としてスピードと柔軟性の両立につながっているのだと思います。
木村氏
思想やグランドデザインといった大枠については、私自身が考えていましたが、次第に社員が主体となり、現場目線でどんどん改良を重ねてくれました。今では、私自身が把握していない仕組みが生まれているほどで、社員主導で進化している部分が大きいですね。
―新しいことに挑戦される際、必要な人材はどう確保しましたか?
また、既存の社員の意識をどう新規事業に向けさせましたか?
鍛治川氏
デジタル印刷事業を立ち上げた時のメンバーは、当初、本業側から移ってきた人員と、新規事業とともに採用した人員の双方で構成しました。この二つの人材が共存したことで、双方が職場にいい雰囲気を作り、新規事業に対しての意識を培っていきました。
もっとも、現場では今も悩みが尽きません。例えば品質に対する考え方です。オフセット印刷部門では、仮に一つでも品質異常が発生すれば刷り直しとなる緊張感があり、再発防止策を詳細に記載する文化が根付いています。一方、デジタル印刷では1枚単位で刷り直しが可能です。その結果、「どこまでを重大なミスと捉えるか」という線引きが非常に難しくなります。そこで損害金額基準を設けるなど、一定のルールを敷いていますが、今なお試行錯誤が続いています。異なる考え方や意識が交差する中で、事業にふさわしい新たな基準をつくり上げていくことが、今後の課題だと考えています。
木村氏
まず人材確保についてですが、既存のメンバーに対して、全く異なる分野の新規事業を任せることはありません。イベント事業や事務局事業といった新しい領域については、主に中途採用の人材に担ってもらう形を取りました。
仕事への意識ですが、フルサービスを実現するには、印刷部門も含めて、請負型製造業の姿勢から、顧客に積極的にアプローチするサービス業的なマインドにシフトする必要があります。保守的な姿勢から、より能動的で行動的な姿勢に、社員の仕事に対する考え方を転換するために、研修やグループワークなどを段階的に取り入れました。また、徐々に権限委譲を進め、社員が主体的に動ける環境づくりを意識してきました。
結果として、既存メンバーには従来業務を中心に担ってもらうのが基本路線ながら、そのうち全体の2割程度が新しい取り組みに関わるようになりました。
―以前、鍛治川さんは自社でシステムを構築する人材を育成したと仰っていました。
鍛治川氏
そうですね。ノーコードツールでシステム開発ができる人材が4人ほどいます。ノーコードツールで補えない部分は外注しています。どこを社内で開発して、どこを外注すべきか、だいぶ明確になったのはこの3年ぐらいで、すごく成長したなって感じています。使用しているのはExcelと同じ感覚で使える「Forguncy」や、非常に自由度の高い「Bubble」です。
木村氏
当社も元々DTPを担当していた社員が、「セールスフォース」を軸にノーコードツールを使って社内のシステムを構築しています。また、IT企業とパートナーを組み、顧客の要望に合わせたシステムの販売も実施しています。システムの自社開発は考えていません。現在、学会運営に特化した事務局向けのAIサービスを開発し、実際に提供していますが、この分野は本当に競争が過熱しています。大手企業もベンチャー企業もAIツールの開発に乗り出し、高性能で便利なツールが次々に登場しており、この市場への参入はリスクが高く、むしろ必要な機能を外部委託した方が負担なく良いツールが得られると判断しました。
鍛治川氏
AIの進歩は本当に驚かされますね。つい最近もGemini3.0がリリースされましたが、劇的に実用性が上がっています。さらに驚くことに、Gemini2.5の発表から3.0まで、まだ半年も経っていないのです。
とくに驚かされたのはコンテンツの生成機能です。私はリリースからずっとGemini3.0に触れ続け、チラシやPOPを試作していますが、どれも店頭に飾れるほどのクオリティです。また、「Google NotebookLM」も進化しました。これはアップロードした資料を元に、自分だけのAIアシスタントが作れるアプリケーションです。例えば、当社の情報をテキストで読み込ませれば、その情報を要約し、当社について解説する資料を作れます。さらにその情報から、イラストや動画まで生成できるのです。試しに「共進ペイパー&パッケージと競合他社を比較する」といった動画を作ってみました。当社の会社説明に十分足りるレベルの動画が、たった10分で生成されます。社会の様々な仕事が大きく変わる予感がします。
―AIに対する脅威とメリットを、どのように捉えていますか。
鍛治川氏
フロントエンド、つまり企画や発想、情報整理といった領域の仕事については、この1年ほどで、今後は劇的に減っていくのだろうと感じています。これは大きなメリットであると同時に、明確な脅威でもあります。
一方で、例えばイーロン・マスク氏も言及していますが、溶接工のような、手を動かしながら対応しなければならない仕事は、今後も一定の価値を持ち続けると思います。私たちの現場作業も、まさにそうした領域に含まれると考えています。
AIによって仕事の在り方は、ますます混沌としていくでしょう。その中で、すべてを拒むのではなく、自分たちなりに咀嚼し、翻訳しながら使いこなしていく必要があると思っています。どうしても適応できない局面が来たら、そのときは撤退するという判断も含めてです。
仮に、AIが「すべてをつくる」時代になったとしても、私たちの「届ける側」としての役割は残り続けると考えています。また、実際に正確なもの、高い品質を求めると、どうしても人の手が介在せざるを得ない領域は残ります。つまり、AIによって置き換わる領域と、人の価値がより高まる領域、この二軸で捉えながら、事業を考えていく必要があると見ています。
木村氏
デメリットとしては、やはり同質化と価格競争です。例えば、生成AIを使って誰でも短時間でデザインを制作できるようになると、必然的に成果物は似通ってきます。使用しているAI自体が共通である以上、プロンプトの工夫による差は出るものの、全体としては同質化が進み、価格が下がっていく流れになる恐れがあります。
一方で、メリットも確実にあります。これまで採算が合わず、ビジネスになり得なかった領域が、新たにビジネスとして成立するようになる点です。例えば当社では、研究者(お客様)の悩みに応えるコンテンツを200、300本ほど蓄積していましたが、AIを活用し、インターン生に解説動画を制作させたのです。具体的には、インターン生が2週間程で約200本の動画を制作し、YouTubeチャンネルに公開しました。その結果、開始からまだ1ヵ月ではありますが、月に約900人の研究者が視聴してくれ、問い合わせも増加しています。従来、研究者の悩み一つひとつに対して5分、10分のプレゼンテーション動画を大量に作るとなると、費用対効果がまったく合いません。しかし、AIによる動画生成ならば多様な動画をほとんどゼロコストで作成でき、高い費用対効果が見込めます。動画によるセールスが十分に経済合理性を持つようになるのです。
鍛治川氏
AIの進化については、正直なところ先行きが見通し切れない部分があります。2026年について言えば、現実的にはエージェント型AIが普及して、見積もりなどの業務効率化を中心とした変化が主になるのではないかと見ています。少なくとも生産現場そのものに、直ちに大きな変化が及ぶとは考えていません。一方で、2年後、3年後を見据えると状況は大きく変わる可能性があります。
木村氏
プログラムコードをAIが生成できるようになったことで、アプリケーション開発のコストは大幅に下がり、多くのベンチャー企業が多種多様なアプリケーションを次々と市場に投入してくるでしょう。そうした中で、有益なアプリケーションが、2026年以降、比較的導入しやすい価格帯で数多く登場してくるのではないかと期待しています。
鍛治川氏
今回のランサムウェア被害のような事案が起きると、大手企業は間違いなくセキュリティを一段と強化していきます。その結果として、出たばかりのソフトウェアやフリーツールについては、「使ってはいけない」と制限されるケースが増えてくると思います。大手企業が身動きを取りにくくなる一方で、規模が小さい企業は、新しいツールを比較的柔軟に導入できるようになりますから、結果として競争力が高まるという現象が起きる可能性があると感じています。小規模のプレーヤーがどんどん便利になっていきながら、大規模のプレーヤーはセキュリティ要件が厳しくなる分、かえって不便になっていくのではないかと思います。
―既にビジネスの中でAIは取り込まれていますか?
木村氏
もう徹底的に活用する方針です。先ほども述べたようにAIによる同質化が迫っていますので、中小企業は早期からAIを活用したビジネスを展開し、固有の領域を開拓しなければなりません。
鍛治川氏
もしどこかの企業がどんな悩みにも応えられるAIを作ったとしたら、学術団体もソウブン・ドットコムさんを頼ることなく、自分たちで問題を解決するようになってしまいますしね。
木村氏
はい。だからこそ、生産設備や製造技術などのフィジカル領域の価値が高まると考えます。
鍛治川氏
私は、印刷業界が今後、明確に二極化が進むと考えています。インキを練るといった高度な職人技や、AIが代替できない極めて付加価値の高い印刷技術を持つ会社は、再評価されていきます。また、企画・デザインに特化した企業も評価を受けるでしょう。一方で、その中間に位置する企業の役割は、消えていく可能性が高まります。生産が集約され、設備力と生産能力を持つ上位の事業者に集中すると、一般的な印刷会社は、コスト面で競争力が低下します。これだけ印刷技術が進めば品質面での差も出にくくなり、市場での価値が低くなるということです。
木村氏
私も今後は生産能力そのものが固有の価値になると考え、デジタル印刷機をベースとしたPOD工場への投資を継続しています。一方で、その領域でも差別化は容易ではありません。印刷物という「モノ」としての価値を打ち出しづらい側面があるのも事実です。そのため、工夫をしなければ、鍛冶川さんがおっしゃった二極化構造の中で、ちょうど中間に位置する会社になってしまう可能性もあると危惧しています。従来とは少し異なる切り口での攻め方を、今後は考えていかざるを得ません。
―鍛冶川さんから木村さんに聞きたいことはありますか?
鍛治川氏
ソウブン・ドットコムさんは顧客と直接接点を持つフロントサービスを主業としていますが、ここはAIの得意領域でもあります。AI技術が拡大する中で、今後の動向をどう予測しますか?
木村氏
今後7年程度は、現在の取り組みをベースに、AI技術を取り込んでいくことで、十分に対価を得られると見ています。ただし、7年後を見据えると、状況は大きく変わる可能性があります。事務局業務一つを取っても、現時点ではAIを活用した事務局機能を当社が提供することができますが、AIの普及がさらに進めば、学会側が自らAIサービスと契約し、事務局業務のインハウス化を進めるでしょう。
実際、クリエイティブ領域ではすでにインハウス化が進んでいます。生成AIによって表現のハードルが大きく下がり、これまで外注していたクリエイティブ関連の業務を自社内で完結できるようになっています。
その流れを踏まえると、事務局業務を含めたフロント業務の多くは、将来的にインハウス化されていくでしょう。この先、当社がどこに価値を見出し、どの領域で関与し続けるのかについては、改めて腰を据えて考える必要があると感じています。まさにこの年末年始に向き合うべき重要な宿題です。
鍛治川氏
最近、デジタル印刷を前提に新たな工場を検討する中で、「30年以上使う前提の建物を、今この事業のために建ててよいのか」とふと考えました。30年後にデジタル印刷を軸にした事業が社会に求められなくなり、建物までが無駄になるかもしれないことが否定できなくなったのです。デジタル印刷事業については、正直なところ、今後5年程度は十分に事業として成り立つと見ています。ただし、7年後、10年後まで持続できるかと問われると、確信が持てません。そのため、今回の工場については「建てる」のではなく「借りる」という判断をしました。いつでも撤退できる、やめられる選択肢を残しておくことが重要だと考えたからです。
以前からよく言っているのですが、私たちパッケージ業界も、もし「どこでもドア」のような技術が開発されたら、一瞬で存在意義を失うと見ています。現時点ではドローン配送などにとどまっており、そこまでの脅威は現実化していませんが、ブレイクスルーが起きて「パッケージは不要になる」と感じた瞬間には、撤退を前提に動かなければならないと思っています。デジタル印刷事業も同様で、何か一つの新しい技術にすべてが巻き上げられると感じた瞬間を気が付いたらやめる準備を始める意識が出始めました。そうなるまでの間に、次の事業の種を考え続けることが、これから先を生き残るためには不可欠なのだと思います。
木村氏
そうですね。AIの急速な進化を見ていると、常に次代の事業を考えながら、今の事業の構築に臨んでいかなければならないと強く感じます。
―木村さんから鍛冶川さんに聞きたいことはありますか?
木村氏
鍛冶川さんが最も会社にとっての脅威を感じていることは何ですか?
鍛治川氏
私が最も強く意識しているのは、セキュリティリスクです。経営に致命的な打撃を受けるとしたら、決定的なセキュリティの穴を当社が開けてしまい、取引先に損害を与えるケースだと思っています。損害賠償に発展するような事態になれば、事業の継続自体が危うくなる。
社員による不祥事や、企業としてのコンプライアンス違反、社会的信用を損なう事故といった今も存在するリスクは引き続き注意すべきです。それに加えて、以前はそこまで大きく捉えられていなかったリスクが、一気に「致命傷」になり得るものとして広がってきていると感じています。リスクの中でも特に怖いのが、大手企業との取引に関わるセキュリティ事故です。売上構成比の大きなお客様のセキュリティに、こちらの責任で穴を開けてしまった場合、取引停止にとどまらず、会社の存続そのものに関わる事態になりかねない。そこは、今もっとも神経を使っている部分ですね。
当社は取引先も分散しており、事業も複数のポートフォリオに分けているため、収益構造自体は比較的堅実だと考えています。だからこそ私は、常に「どうしたら会社が潰れるか」を先に考え、会社のリスクになること側を徹底的にケアするよう動いています。
2026年は事業環境が劇的に変化する
―2026年をどう展望していますか?
鍛治川氏
2026年は、とにかくAIによって顧客の要望や事業環境が劇的に変わる年になると見ています。おそらくOpenAIをはじめ、確実にそれを一段階押し上げるようなアップデートが出てくるでしょう。
そうした中で、当社としては今が「第2期の成長期」にあたると考えています。事業のフィールドを広げながら、AIの導入や自動化を一気に進め、デジタル印刷を軸とした生産特化型の体制を目指していきたい。そのための基盤づくりに注力する1年にしたいと考えています。
また、こうした成長を見据え、来年には新たな拠点の構築も視野に入れています。変化のスピードが速い時代だからこそ、柔軟に動ける体制を整えつつ、次の成長につなげていきたいと考えています。
木村氏
当社は2026年を、AIのキャッチアップと実装、そして事業への展開に相当注力する年にしていきます。ただ、それだけでは不十分であり、人の能力を引き上げていくことも同時に進めなければなりません。AIの活用と人材育成、この二軸を並行して進めていくことが2026年の大きなテーマになると思っています。
その中で、今日の議論で最も印象に残ったのは、「フロントをどうするのか」という鍛冶川さんからの問題提起でした。AIエージェントによるインハウス化が進むなか、どう新たな価値を生み出していくか。ここについては、この1年をかけて、自社なりの解とビジョンを見出していきたいと考えています
- 株式会社共進ペイパー&パッケージ
- 代表取締役社長 鍛治川 和広
- 神戸市中央区元町通6-1-6 共進ビル
- https://www.kyoshin-pk.co.jp/
- 株式会社ソウブン・ドットコム
- 代表取締役社長 木村 崇義
- 東京都荒川区西尾久7丁目12-16
- https://www.soubun.com/